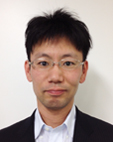| F5d | 7月25日 | 15:15〜16:55 | 会議室D | |||||
|
||||||||
|
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 ソリューションビジネス推進本部 コンサルティング1部 部長 |
|
独立行政法人 情報処理推進機構 ソフトウェア・エンジニアリング・センター エンタプライズ系プロジェクト 研究員 |
| 組織目標達成とIT導入の整合性を図るために |
| 〜GQM+ストラテジーの紹介〜 |
|
1983年に日立に入社。半導体製造、検査装置の組み込みソフト系のエンジニアを経て、半導体工場MES系の開発、生産管理システム開発のプロジェクト・マネージャを経験。2003年より現勤務先に移り、システムコンサルティングに従事。主にIT戦略、システム企画・計画、要求分析等の超上流を担当し、現在に至る。 最近では、ユーザ企業の情報システム部門が変わらなければ、日本の企業のIT活用は向上しないとの考えに至り、情報システム部門変革に向けた取り組みに力を入れている。 IPA/SECにおいては、2010年度よりプロセス改善WG(NPT5)に委員として参画。そこで出会ったGQM+ストラテジー手法の研究に従事し、今年度からは多くの企業への普及展開を実施する予定。 |
|
1999年に大同生命保険のシステム部門に配属(後に、T&D情報システム(株)に出向)。 システム開発現場における基幹系システムのSEや情報系システムのリーダー、本社企画部門におけるシステム化計画の策定・推進担当を経験。 2012年よりIPA/SECに勤務し、現在に至る。 IPA/SECにおいては、要求発展型開発WGやGQM+ストラテジー手法の研究を行う戦略意志決定WGなど、主として超上流の検討WGに参画。 |
|
ソフトウェア開発プロジェクトにおいては、何のためにそのソフトウェアが使用されるかということを十分に考えた開発が行われなければ、使いものにならないと評価される、いわゆる「動かないコンピュータ」となる。また、多くのソフトウェア開発プロジェクト間の優先順位についても、単に大きな声に従うというものではなく、関係すると推定される複数の要素を十分考察しないと期待された成果を出し難いと考えられる。 このような問題に対応するために、経営企画部門、業務部門および情報システム部門等において客観的判断を行える手法が求められている。 SECでは、ドイツ・フラウンフォファー協会IESEからのGQM+ストラテジーという手法を複数の企業において試行し、どのように導入すれば日本で有効に活用できるかの共同研究を実施してきた。 当セッションにおいては、ある会社での試行から得られたものをベースにして、SEC作業部会において検討してきたものを、紹介する。 なお、GQM+ストラテジーに関する詳細な最新の資料は英語および日本語(6月に予定)版がSECホームページから入手可能である。 |
| F5d | 7月25日 | 15:15〜16:55 | 会議室D | |||